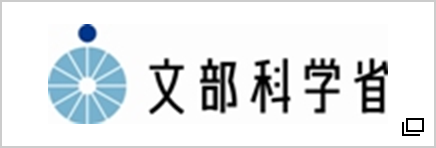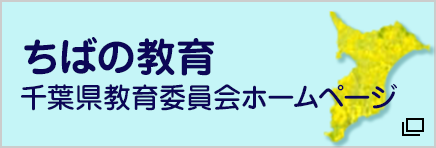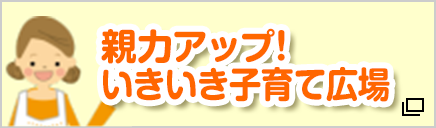校長挨拶
更新日:2026年02月05日
校長挨拶
令和8年2月5日(木)
一昨日は節分でした。ご家庭でも豆まきをされたでしょうか。学校では、給食に出た豆を食べながら、「おうちでもやったよ」「鬼はお兄ちゃんだったよ」と、子どもたちが嬉しそうに話す姿が見られました。何気ない会話の中から、家庭でのあたたかな時間が伝わってくるひとときでした。先日、子どもたちに「自分から追い出したい鬼は何かな?」と聞いてみました。今年の1年生から多く聞かれたのは、「泣き虫鬼」「宿題をすぐやらない鬼」「ねぼすけ鬼」など、自分自身の生活や行動に目を向けた答えでした。中には、「鬼がたくさんいすぎて、どれから追い出せばいいかわからない」と話す子もいました。その姿に、「できていないこと」だけでなく、「今、できていること」や「がんばっている自分」にも目を向け、自分を大切に思う気持ちを育てていくことの大切さを改めて感じました。実は、今の2年生も1年生だった頃には、今の1年生と同じような答えを書いていました。ところが今年、同じ問いかけをしてみると、「いじわる鬼」や「いらいらすると友達にあたってしまう鬼」など、人との関わりの中での自分の姿を振り返る言葉が多く見られるようになりました。同じ「鬼」を追い出すという問いであっても、学年が上がるにつれて、子ども達の目は「自分だけ」から「他の人との関わりの中の自分」へと向かっていきます。そこには、「もっとやさしくなりたい」「もっと相手の気持ちを考えられるようになりたい」という思いが感じられ、少しずつ成長している姿を、頼もしく感じました。
今月は、教室を離れての活動や、外部の方から直接お話を聞く体験学習が多くありました。1年生は校庭でたこあげをしました。冬の空を見上げながら、自分で作ったたこが空高く舞い上がる様子に、大喜びでした。2年生は町探検に出かけ、地域のお店や施設を見学させていただいたり、そこで働く方のお話を聞いたりしました。実際に足を運び、地域の方と直接関わる中で、「まちの中には、たくさんの人の仕事や思いがある」ということに気づく貴重な学びとなりました。ご協力くださった地域の皆様には、心より感謝申し上げます。また、5・6年生は被爆体験伝承講話を通して、平和の大切さについて考える機会をもちました。実体験に基づく言葉に真剣に耳を傾け、自分たちの生き方や、未来に引き継いでいく責任について考える姿が見られました。このように、体験を通した学びは、知識を得るだけでなく、人と出会い、心を動かし、自分と社会とのつながりを実感する大切な機会となります。様々な立場の人との関わりの中で、少しずつ視野を広げ、確かな成長を重ねています。年の始まりに、こうした学びを積み重ねられていることは、子どもたちにとっても、学校にとっても、とてもよいスタートになっていると感じています。
市内ではインフルエンザが流行し、学級・学年閉鎖を余儀なくされている学校も少なくありません。そのような中、本校の子どもたちが概ね元気に学校生活を送ることができているのは、日頃からの保護者の皆様のご協力のおかげと、心より感謝しております。なお、一部の学年ではインフルエンザの罹患が見られる状況もございます。引き続き、子どもたちの健康管理と、規則正しい生活へのご配慮を、よろしくお願いいたします。
令和8年1月9日(金)
あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。年末年始は、ご家庭でそれぞれに大切な時間を過ごされたことと思います。
短い冬休みを終え、学校には子どもたちの元気な声が戻ってきました。休みの過ごし方や準備の状況は一人一人異なりますが、子どもたちが気持ちを整えながら新しい学期に向かえるよう、教職員一同、温かな生徒指導と丁寧な支援を心がけてまいります。
さて、今年は午(うま)年です。馬は、一歩一歩、大地を踏みしめながら前へ進む動物です。急がずとも、止まらずに進むことを大切にしながら、「うまくいく一年」にしてほしいという願いを、子どもたちに伝えました。こうした思いは、これから始まる3学期の過ごし方にも重なります。
3学期は、今の学年で過ごす最後の3か月です。一年を振り返り、「楽しかった」「よくがんばった」と笑顔で締めくくるとともに、次の学年へと向かう大切な準備期間でもあります。特に6年生にとっては、中学校生活を見据え、自分の課題に向き合いながら一歩踏み出す時期となります。
そして、この「挑戦」というテーマは、世界で活躍する人々の姿からも学ぶことができます。2月には冬季オリンピック、3月にはワールド・ベースボール・クラシックなど、世界の舞台で挑戦する選手たちの姿に触れる機会があります。努力を重ね、挑戦する姿から、あきらめずに取り組むことや、応援する気持ちの大切さを感じ取ってほしいと願っています。
始業式では「曼荼羅(まんだら)チャート」という考え方を、一つのアイデアとして子どもたちに紹介しました。「どんな自分になりたいか」「そのために今できることは何か」を考え、紙に書いてみるという、目標を見える形にする方法の一つです。学校としての取組という位置づけではありませんが、子どもたちが自分自身を見つめるきっかけになればと考えています。また、校長室の前に、手作りの「絵馬」を飾るスペースを用意しました。自分の願いを書き、みんなでそれを見合い、お互いの幸せを願い合える——。そんな温かな雰囲気で、この3学期をスタートさせたいと考えたからです。
現在、校長室前にはたくさんの絵馬が並んでいますが、その中に「ともだちとなかよくなりたい」と書かれたものを見つけました。そんな小さくも真っ直ぐな願いに、見ているこちらまで思わず笑顔になり、心がぽかぽかと温まるのを感じました。自分のことだけでなく、誰かの幸せをそっと応援できる。そんな優しさにあふれる学校生活を、今学期もみんなで形にしていければと願っています。
3学期も、子どもたち一人一人の成長を大切にしながら教育活動を進めてまいります。 本年も、本校の教育活動へのご理解とご協力を、どうぞよろしくお願いいたします。
令和7年12月19日(金)
早いもので、令和7年も残りわずかとなりました。日頃より、本校の教育活動に温かいご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。11月から12月にかけては、子どもたちが多くの人と関わりながら成長する姿を、さまざまな場面で見ることができました。
修学旅行では、道路事情により鎌倉での班別行動の時間が短くなる場面もありましたが、子どもたちは互いに声をかけ合い、相談しながら見学を進めていました。役割を意識して行動し、友達と食事や入浴の時間を共に過ごした二日間は、仲間と協力する大切さを実感する、思い出深い経験になったことと思います。秋の行楽シーズンという条件も踏まえ、今後もできる限り計画どおり活動できるよう工夫してまいります。こうした行事で培われた「やり抜く力」は、日常の学習や運動にもつながっています。
マラソン記録会では、友達を意識して挑戦する子、予行練習の自分と比べる子、最後まで走り切ったことを喜ぶ子など、一人一人が自分なりの目標をもって取り組んでいました。得意不得意はあっても、自分自身と向き合い、最後までやり切ろうとする姿を大切にしたいと考え、今年も全員に記録証を贈っています。こうした経験が、これからの学習や生活に向かう力につながっていくことを願っています。 また、PTAお楽しみ会では、会場いっぱいに子どもたちの笑顔があふれていました。「子どもたちの笑顔のために」と、忙しい中でも時間をやりくりして準備してくださった菅谷会長をはじめ、PTAの皆様、おやじの会の皆様、読み聞かせボランティア菜の花の皆様に、心より感謝申し上げます。
12月の授業参観・保護者会にも多くの方にお越しいただき、ありがとうございました。本校では、年に一度、道徳の授業を公開しています。自分の考えをもち、友達と語り合いながら、よりよい生き方を考える授業を目指しています。タブレットの活用については、授業のねらいや学習内容に応じて、取り入れ方には幅があります。だからこそ、どの学級でも子どもたちが「考え、伝え合う」学びに向かえるよう、授業を見合い、話し合いながら、学校全体で授業づくりの改善に取り組んでいます。すぐに同じ形になるものではありませんが、一つ一つの実践を大切にしながら、子どもたちの深い学びにつながる授業を目指してまいります。よろしくお願いいたします。
冬休みには、ぜひお子さんと一緒に宿題に取り組み、頑張りを認め、苦手なところを共に考える時間を大切にしてください。書き初めの宿題も、日本の伝統文化に触れ、心を落ち着けて文字と向き合うよい機会です。おうちの方が向き合ってくださることが、子どもたちの大きな励みになります。
皆様のご健康とご多幸をお祈りするとともに、本年も大変お世話になりました。 どうぞよいお年をお迎えください。
令和7年11月7日(金)
秋も深まり、校庭の木々も少しずつ色づき始めました。10月の運動会では、子どもたちの笑顔と真剣なまなざしが輝いていました。今年は赤組が数年ぶりの優勝。惜しくも敗れた白組の中には、涙を流して悔しがる姿もありました。それほどまでに全校児童が「一致団結 全力つくせ」のスローガンのもとに心を一つにして取り組んだ証だと感じました。昨年より一つ学年が上がり、下級生に優しく声をかけたり、長い距離を力強く走り抜けたりする姿に成長を感じ、頼もしさで胸が熱くなりました。初めての運動会となった1年生の全身で踊り走る姿には、地域の保育園の先生方も感動されていました。3、4年生のダンスは、校庭いっぱいに花が咲いたようで見ている人を笑顔にしてくれました。5、6年生は大きなかけ声とともに力強く踊り、下級生から「かっこいい」と憧れのまなざしを向けられていました。何かに一生懸命取り組み、心を動かす瞬間を味わうことは、とても大切だとあらためて感じました。温かい声援をおくってくださった保護者の皆様、本当にありがとうございました。運動会を通して、子どもたちはたくさんの達成感と絆を得ることができました。
さて、6年生は、過日行われました二部会音楽発表会に学年として参加しました。課外活動の合唱部で参加する学校もある中、新山小の子どもたちは学年全員で心を合わせてステージに立ちました。曲は「絆~キミとボクとのたからもの~」。明るくまっすぐな歌詞が、子どもたちの姿と重なり、美しいハーモニーが会場いっぱいに響き渡っていました。
11月7日からは「読書郵便」が始まります。おすすめの本を紹介し合いながら、読書を通して心をつなげていく取り組みです。5日からはマラソン練習も始まり、校外学習やなかよし発表会なども予定されています。スポーツや読書、芸術など、それぞれが目標や楽しみを見つけ、充実した秋を過ごしてほしいと思います。子どもたちの中に、また新しい「がんばる芽」が育っていくことを楽しみにしています。
令和7年10月7日(火)
実りの秋を迎えました。おいしい食べ物、さわやかな空気、そして秋の夜長にゆっくりと読書に親しむ時間…。皆さまは、どんな秋をお過ごしでしょうか。
9月はまだまだ暑い日が続きましたが、子どもたちは元気いっぱいに学校生活を送ってくれました。警報やアラートが出て校舎内での活動が多くなった時期には、図書館司書の工夫で「読書ビンゴ」に取り組むことができました。いろいろなジャンルの本を手に取るきっかけとなり、読書の輪が広がっています。また、読み聞かせボランティア「菜の花」の皆さんの継続的な活動もあり、学校全体が本に親しむ雰囲気に包まれています。「おうちの人が本を読んでくれるのがうれしい」と子どもたちから聞く機会も増え、ご家庭でのご協力をとてもありがたく思っています。大人が本を読む姿や、小さなお子さんへの読み聞かせは、自然と子どもが本に親しむきっかけになるそうです。ぜひ、ご家庭でも“本のある時間”を楽しんでいただければと思います。さらに、9月には新体力テストにも取り組みました。どの学年の子も一生懸命に挑戦し、自分の力を出し切ろうとする姿が見られました。特に、6年生と1年生、5年生と2年生がペアとなり、3年生や4年生も計測や応援を通して助け合う場面はとてもほほえましく、学校全体に温かな雰囲気を広げてくれました。
本といえば、読書週間にあわせて給食センターと図書室とのコラボ企画「本から飛び出した給食」が実施されています。本に登場するおいしい料理が給食に登場する企画で、今月はなんと7冊の本からメニューが選ばれています。中には実際の作り方が紹介されている本もありますので、ぜひお子さんと一緒に作ってみてはいかがでしょうか。
心も体も豊かに育つ秋、子どもたちがたくさんの本と出会い、体も心も元気に過ごせるよう、これからもご家庭と学校とで見守っていきたいと思います。
令和7年9月5日(金)
長い夏休みを終えて、新山小に子どもたちの元気な声が戻ってきました。やはり、子どもがいてこそ学校は学校らしく輝くのだなと、あらためて感じています。
さて、本校では「自分にされていやなことは、人にしない」という約束を、子どもたちとともに大切にしています。これは子どもだけでなく、教職員を含めて新山小で過ごすすべての人の共通の約束です。昨年度から呼びかけを続け、2年目の今年は子どもたちの中にしっかり根づいてきたように思います。教室で遊んでいる子どもたちが、おもちゃの貸し借りや順番を決めるときに「校長先生が言ってるでしょ、自分にされていやなことはしちゃいけないんだよ」と声をかけ合う姿を見かけると、本当にほほえましく、嬉しい気持ちになります。小さな場面ではありますが、そこには「相手を思いやる心」が確かに息づいています。こうした姿は、学校だけでなくご家庭でも表れていることと思います。お子さんが家族や友達に優しくできたこと、思いやりをもって行動できたことにご家庭で気づいたら、ぜひたくさんほめてあげてください。そして、その様子を担任にもお知らせいただければ、学校でも一緒に喜び合い、さらに子どもたちの成長につなげていきたいと思います。
2学期は、運動会や音楽発表会をはじめ、多くの行事があります。子どもたち一人ひとりが、学習や行事の中で自分の良さを発揮し、仲間と力を合わせる経験を重ねていく時期です。私たち教職員も1学期を振り返りながら「優しい自分」でいられるよう心がけ、これからの毎日を誰とでも温かな心でつながり合える学校にしていきたいです。2学期も、子どもたち一人ひとりが安心して学び、成長できるよう、教職員一同力を尽くしてまいります。引き続き、よろしくお願いいたします。
令和7年7月3日(木)
早いもので、今年も折り返しを迎えました。日ごとに暑さが増し、夏本番の訪れを感じる季節となりました。先日、「高校生のなりたい職業は10年連続で『教員』が1位だった」という記事を見かけました。小学4~6年生では10年間変わらず「プロスポーツ選手」が1位、中学生では『教員』が8回も1位になっているそうです。興味深いのは、小学5年生のときに思い描いた夢を、高校2年生になっても持ち続けている生徒が3人に1人以上いたという点です。一方で、夢が変化していった子どもたちの多くは、素敵な先生との出会いや、将来の進路について深く考える経験を通して、自分の道を見つけていったことがわかったそうです。
本校の6年生も、総合的な学習の時間に「職業調べ」に取り組みました。まず、タブレットを使ってベネッセの職業適性検査を行い、自分の「興味・関心」や「秘めた能力」に合った職業を知ることから始めました。そして、気になった職業について調べ、スライドにまとめて発表しました。子どもたちは、自分たちの生活を支えるさまざまな仕事について理解を深めるとともに、自分の強みや課題についても気づき、将来の夢をさらに広げるきっかけになったようです。
夢は遠くにあるようでいて、実は日々の中にある小さな「希望」の積み重ねの先にあります。例えば、失敗してもあきらめずにまた挑戦してみること、誰かにやさしくすること、――その一つひとつが、夢へと続く道になっていきます。もうすぐ、子どもたちが楽しみにしている夏休みがやってきます。この機会に、ご家庭でも「将来の夢」について話題にしてみたり、夢に関する本を読んだり、調べたり、挑戦してみたりするのも、きっと素敵な時間になることと思います。長い夏休みを、ご家族とともにゆったりと過ごしながら、子どもたちの心が豊かに育つような経験ができたらと願っています。
校長室の前には、七夕の短冊を飾っています。子どもたちや教職員が書いた「願いごと」や「夢」が並んでいます。「宿題がなくなりますように」といった微笑ましい願いから、「新山小の先生になりたい」といった嬉しい夢まで、さまざまな思いが込められています。ひとつひとつの短冊が、未来への第一歩となることを願ってやみません。いよいよ夏本番。まずはこの7月を、元気に、安全に、そして笑顔で過ごしていきましょう。1学期、ご理解とご協力いただき、ありがとうございました。
令和7年6月4日(水)
6月になりました。校庭のすみにアジサイの花が色づき、雨の日にはカタツムリの姿も見かけるようになりました。
さて、みなさんはカタツムリが「歯」をたくさん持っているって知っていましたか? なんとその数、2万本以上!人間の歯が大人で32本ですから、すごい数です。でも、たくさん歯があっても、カタツムリには歯みがきの習慣はありません。虫歯になってしまったら、きっと大変ですね(笑)。ところで、私たち人間にも6月に大切なイベントがあります。それが、5月・6月に実施している歯科検診です。検診の結果から、虫歯が見つかることもありますが、それは「自分の歯と向き合うチャンス」でもあります。先日、2年生の子が自分の歯を見せながら、「7本、大人の歯になったんだよ!」と誇らしげに教えてくれました。また、前歯が2本抜けている子が「とうもろこしが食べられない〜」と笑顔で話してくれる場面もありました。歯は一生の宝物。虫歯が見つかったら積極的に治療し、そして日ごろのケアが何より大切です。しっかり歯をみがいて、大切な歯をずっと元気に保ちましょう。
梅雨の季節は外で遊べない日もありますが、そうした時こそ、ゆっくり周りを見て、聞いて、感じるチャンスです。自然や自分の体に目を向けて、新しい「気づき」を楽しんでほしいと思います。そんな中、最近うれしい出来事がありました。1年生の子どもたちが、昼休みに校長室に遊びに来た時のことです。「一緒にトランプをしよう」「折り紙やりたいけどうまく折れないから教えて」「にいやワン(新山小のキャラクター)が上手に描けたよ」と、笑顔いっぱいで話しかけてくれます。その中で、2年生が折り紙の折り方を教えてあげたり、「いっしょにやろう」と声をかけてあげたりする姿が見られ、思わず心が温かくなりました。
ある雨の日、ふたば・わかば学級で子どもたちと遊んでいたところ、なんとその1・2年生たちが私を探してきてくれました。みんなでミニカーを走らせたり、ブロックを組み立てたりしながら楽しく遊ぶ時間が生まれました。学習だけでなく、子どもたちの得意な遊びややりとりの中で、自然と交流が生まれる。そんな温かな場面を、これからも大切にしながら、一人ひとりの成長を見守っていきたいと思います。
令和7年5月2日(金)
緑のまぶしい季節となりました。4月には、かわいい1年生を迎え、学校にたくさんの笑顔があふれました。入学式では、少し緊張した様子だった子どもたちも、今では少しずつ学校生活に慣れ、元気に「おはようございます」とあいさつしてくれるようになりました。教室では、先生や友だちとひらがなや数字を学び、昼休みは元気いっぱいに遊んでいます。給食当番や掃除など、できることが増える喜びを感じながら毎日生き生きと活動しています。また、図書室や教室の本棚から、お話の本を手にとり、自分から進んで読む子どもたちの姿もたくさん見られます。
さて、4月の授業参観、保護者会へのご出席ありがとうございました。おかげさまで各学級、学年の役員さんも決まり、今年度のPTA活動も順調にスタートできました。新学期がスタートしてから1ヶ月。お子様の様子はいかがでしょうか。朝、校内を歩いていると、昨年度に比べて遅刻や欠席が減っていることに気が付きました。整えられた教室で、子どもたちが背筋を伸ばして先生の話を聞いたり、静かに本を読んだりしている姿に、子どもたちのやる気とご家庭での温かい支えを感じ、嬉しく、またありがたく思っております。高学年の5・6年生は、委員会活動や「すくすく班(縦割り班)」活動のリーダーとして、掃除の仕方をやってみせながら下級生に教えたり、学校のためにできることを考えたりと、張り切って取り組んでいます。また、課外活動では、5月14日に行われる部会陸上大会に向けて、練習も始まりました。仲間とともに目標に向かって努力する姿が、とても頼もしく感じられます。
これからも、一人ひとりの歩みに寄り添い、楽しい学校生活を送れるように、教職員一同で見守ってまいります。ご家庭でも、お子さんのがんばりをたくさんほめていただければと思います。
令和7年4月7日(月)
春の日差しの中、子どもたちが一つ学年を上がり、新しいスタートを切りました。進級、おめでとうございます。始業式の日、久しぶりに会う友達と笑顔で言葉を交わし、新しい学級や友達、先生との出会いに胸を弾ませる子どもたちの姿がありました。その明るい雰囲気の中、本校も新たに8名の教職員、5名の転入生を迎え、令和7年度のスタートを切りました。
今年度も、昨年度に引き続き『夢に向かって 心豊かに たくましく生きる児童の育成』を教育目標に掲げ、校訓である「みんななかよし 丈夫に育て」を合言葉に、子どもたちが安心して学び、仲間とともに成長できる学校をめざします。教職員一同、「チーム新山」として力を合わせ、誰一人取り残さない温かな教育活動を進めてまいります。お子様が毎日元気に学校生活を送れるよう、安全を第一に考え、温かく見守ってまいります。今年度も、保護者の皆様のご理解とご協力をいただきながら、家庭、地域と学校が共に支え合い、子どもたちの成長を育んでいければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
令和7年3月28日(金)
4月を迎えるに当たって、だいぶ暖かい日も増えてきました。子どもたちを見守る校庭の桜の蕾も膨らみ始め、新一年生が入学してくる4月には、きれいな花々を咲かせてくれることでしょう。
去る、3月17日に卒業式が行われ、39名が門出の日を迎えました。卒業証書授与では、一人一人が登壇し、将来の夢や決意を述べた後、校長からはなむけの言葉をかけられ、卒業証書を手にしました。式場となった体育館いっぱいに、卒業生の思いはもちろん、在校生、保護者、来賓、教職員の思いが溢れる温かい式となりました。卒業生の別れの言葉「あいしてる 新山小学校 最高の在校生と 最強の先生方に支えられて 今日、私たちは卒業します」という言葉に、思わず涙がこぼれそうになりました。続く言葉には、学校生活の思い出やお世話になった方々への感謝の気持ちが込められ、子どもたちが充実した日々を過ごしたことが感じられました。見送りでは、在校生から手紙を受け取ったり握手をしたり、保護者の方々や教職員が見守る中、多くの祝福や激励の言葉に送られ、晴れ晴れとした表情で新山小学校を巣立っていきました。
学校はある意味、人生の縮図です。毎日、良いことも悪いこともさまざまな出来事が生じますが、それは生きている証でもあり、人との繋がりの中で生きているからこそ起こることです。在校生が贈った歌「ぼくの太陽」の歌詞、「君が育ててくれた 大切なつぼみ いつか大きな花を 咲かせてみせるから 君はぼくを照らしてくれる太陽」のように、6年生は中学校で、在校生は新しい学年で、それぞれ自分らしい花を咲かせてくれることを楽しみにしています。
一年間、たくさんのご支援、ご協力をいただき、心より感謝申し上げます。保護者の皆様の温かいご理解とご協力のおかげで、子どもたちは安心して学校生活を送ることができ、また、素晴らしい成長を遂げることができました。これからも、学校としてより良い環境を作り、子どもたちが成長できるように力を尽くしてまいりますので、引き続きご支援、ご協力いただけますようお願い申し上げます。 ありがとうございました。
令和7年1月8日(水)
新年明けましておめでとうございます。皆様におかれましては、健やかに初春をお迎えのこととお慶び申し上げます。本年も、どうぞよろしくお願いいたします。今年は、十干十二支で「乙巳(きのとみ)」です。「乙巳」の「乙」は植物が目を出して伸びる様子、「巳」は成長のピークを表すと言われています。そのため、新たな成長と飛躍の年、 幸せな未来をつかむ年と考えられているそうです。
年の始まりにあたり、始業式では子どもたちに「初夢」や「一富士二鷹三茄子」といった日本の伝統的な縁起物についてお話ししました。初夢は新年に初めて見る夢のことで、かつては「大晦日から元旦に見る夢」、現在では「元日から1月2日に見る夢」とされることが多いそうです。その中でも「一富士二鷹三茄子」の夢を見ると縁起が良いといわれており、それぞれ「無事」「高い」「成す」にかけた意味が込められています。さらに、今年は「巳年(へびどし)」ということで、へびが「脱皮を繰り返し成長する」ことから、「再生」や「成長」を象徴する動物とされていることもお話しました。この話を通して、子どもたちが夢や目標を持ち、それに向かって前向きに挑戦していける一年になるよう願いを込めました。また、巳年にちなんで、私自身も新しいことに挑戦してみようと編み物を始めました。子どもたちに、私が作ったカメの編みぐるみ(写真右下)を紹介し、つけてある名前をお伝えしました。そのうえで、「こんな名前もどうかな?」というアイデアがあれば教えてほしいと声をかけました。
さて、毎年、担任をしていた子どもたちから年賀状が届きます。今年も受け取り、一通の中にこんな言葉がありました。『日本代表として国際大会に出場し、金メダルを取ってくるから待っていてね。』小学校1年生の頃からオリンピック出場という大きな夢に向かって努力を重ねてきた彼が、着実にその夢に近づいていることに胸を打たれました。その夢がどれほど大きくても、諦めずに努力を続けることで手が届くのだということを、彼の姿が教えてくれているように感じました。子どもたちが自分自身の可能性を信じ、何度でも「脱皮」するような成長を重ねていけるよう、学校職員一同で育ててまいります。保護者の皆さまにもご協力をいただけると幸いです。本年が皆さまにとっても素晴らしい一年となりますように。
この冬はインフルエンザなど急性呼吸器感染症の流行がささやかれています。3学期の登校日数は、40~50日程と短いです。教室では、加湿器を使って加湿をしたり、換気をしたりと感染予防に努めています。ご家庭でも十分な睡眠とバランスの良い食事を心がけ、病気にかかりにくい(かかっても重症化しにくい)体づくりにご留意ください。3学期も引き続き、ご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。
令和6年12月23日(月)
寒くなるにつれて空気は澄み、新山小学校は木々が冬支度を始めています。日本列島では降雪のニュースも聞かれるようになりました。今年はいつにもまして、インフルエンザが流行しており、手洗いやうがいの励行をしています。ご家庭におかれましても継続していただき、健康に2024年を締め、笑顔で2025年を迎えていただきたいと思います。
振り返れば、この一年も子どもたちは日々さまざまな経験を積み重ね、大きな成長を遂げました。学習や運動、行事を通じて得た多くの成果は、保護者の皆さまの温かい見守りと励ましがあってこそだと深く感じております。特に運動会やマラソン記録会では、競技を通じてチームワークの大切さを学び一人一人が目標に向かって頑張りました。校外学習や修学旅行では、日常と異なる環境で過ごし友達の良さに気付き自信に繋がる経験ができました。わくわく広場やPTAお楽しみ会など、皆さまのご支援が子どもたちにとって貴重な思い出となりましたことを、この場を借りて厚く御礼申し上げます。4月から振り返ると、新山小の子ども、職員が健康で過ごせたことに心から感謝の気持ちでいっぱいです。また、家族の支えがどれほど大きなものかを改めて実感した一年でもありました。子どもたちの成長を間近で見守りながら、喜びとともに私自身も成長する機会をいただきました。学校でのさまざまな活動に携わることで、多くの方々と関わり、学ぶことも多くありました。この一年、保護者の皆さまや地域の方々の温かいご支援に心より感謝申し上げます。
来年も、健康第一で、家族とともに笑顔あふれる日々を大切にしていただきたいと思います。 新年度も、引き続き子どもたちが安心して学び、成長できる学校づくりに努めてまいります。どうぞ変わらぬご理解とご協力をお願い申し上げますとともに、来年が皆さまにとりまして素晴らしい一年となりますことをお祈り申し上げまして、年度末のご挨拶とさせていただきます。
令和6年11月8日(金)
2学期がスタートしてから2ヶ月が経ち、その間、後期がスタートしました。その間、たくさんの校内外行事が実施されました。一人一人が役割をもち責任を果たし自信をつけたり、個々の力を学級、学年の集団に集結することでより充実したものになったり、多くの人と関わることでコミュニケーション力を伸ばしたりと・・・どの行事においても心豊かに育っていることを感じました。先日、特別支援学級の子どもたちが学区のなかよし発表会に参加しました。3学級合同での練習では、上級生が下級生に「こっちだよ」と手招きしたり「みんな行くよ」と少し照れながらリードしたりする場面が見られました。また音楽発表会に向けた壮行会では、6年生の合唱を聴いた下級生が「6年生のようにうまくなりたい」「来年はどんな歌を歌うのかな」と美しいハーモニーに憧れの眼差しを向けていました。こうして子どもたちの思いが引き継がれ、新山小の伝統をつくっていくのだと温かい気持ちになりました。
10月21日(月)に運動会が実施されました。開会式には隠れていた太陽も子どもたちの笑顔と声援により顔を出し、爽やかな秋晴れの中、大きなけがもなく終えることができました。赤白の別なく互いを応援したり、力いっぱい走ったり楽しく踊ったり、ゴールして仲間とハイタッチし合ったり・・・競技も応援も一生懸命な姿に感動しました。また、全校のためにグラウンドを縦横に走りながら係活動をする高学年の子どもたちに、大きな拍手を贈りたいです。来賓として参観された新山保育園の園長先生も、「園を巣立った子どもたちが心も体もたくましくなり、本当に嬉しいです。ありがとうございます。」と喜んでいました。卒園後も子ども達を今なお見守っていただいていることにあらためて感謝しました。こうした地域・保護者の皆様の温かい声援と拍手を受け、まさに『あきらめずに、全力で、思い出に残る運動会にしよう』のスローガン通り、新山小全員が楽しむ運動会となりました。結果は、白組が接戦を制して優勝に輝き、紅白リレーも白組が勝利しました。
保護者・地域の皆様、この度の運動会の運営に際しまして、天候により延期となりましたがご理解ご協力いただきありがとうございました。今後も本校の教育活動に、ご理解とご支援をよろしくお願いいたします。
「霜月」この漢字、読める人いるかな?と全校集会で子どもたちに質問したところ、「しもつき」と4年生の男の子が大きな声で答えてくれました。みんなで拍手を送った後に、霜月は11月を表し「霜が降りるくらい寒くなる月」という意味であることを話しました。この話は、「寒い」というキーワードを引き出すためにしたものです。ここから、本当に話したい「ありがとうの反対は・・・ あたり前」に繋げるために、「寒い」の反対語を質問してから「ありがとう」の反対語を質問しました。子ども達が口々に返した言葉は、何だと思いますか?それは、「ごめんなさい」でした。学校や家庭で「ありがとう」「ごめんなさい」を言える大切さを学んでいるためでしょうか。子どもの素直さを感じながら、正解は「あたりまえ」と答えると「えー!」と驚きの声があがりました。「ありがとう」を漢字で書くと「有り難う」になります。「あることが難しい、まれである」という意味です。だから「ありがとう」の反対語は「あたりまえ」となります。そこで、今度は、何か特別なことをしてもらったときや助けてもらったときに「ありがとう」と言いますが、もしお客さんや患者さんのときは、どうしているか投げかけました。「あたりまえ」だと思っていることも、実はたくさんの人に支えられている、決して「あたりまえ」ではないことがたくさんあります。例えば、ご飯を食べられること、元気に学校に通えること、お弁当を作ってもらうこと、楽しい話をして笑うこと、そしてまた明日がくるということ・・・探せばたくさんあります。あたりまえだと思っていることも、あたりまえだと思うのか、感謝の気持ちをもって生活するのか、家族でも友達でも・・・自分のために何かをしてくれた全ての人に対して、謙虚に「ありがとう」と心から思えるか、そして言葉で伝えられるか。1日にいくつもの「ありがとう」があるはずです。「あたりまえ」を「ありがとう」に変換して、温かい学校にしていきたいです。
余談ですが、子どもたちに人気の漫画『ONE PIECE』の登場人物は、何かをしてもらったり助けられたりしたときは「ありがとう」と言っています。これは、作者の尾田栄一郎さんの「ありがとう」とストレートに言えることに対しての思いがあるからだそうです。
令和6年9月3日(火)
長い夏休みが終わり、子どもたちの元気な姿が戻り、学校も息を吹き返したように活気があふれています。例年にない猛暑でしたが、地区の納涼祭、スプラッシュ祭り、こわいお話会など学校とは違う場で子どもたちの笑顔を見ることができました。こうした経験ができるのも夏休みのよさです。その夏休みについて、「いらない」というニュースが話題になりました。夏休みは子育て家庭にとって普段学校に通うこどもたちの食費や光熱費など金銭面での負担が増えるほか、特別な体験をさせる経済的・時間的な余裕がないなど、いわゆる「体験格差」に悩むことが理由のようです。また、ここ数年は、夏休みの宿題が廃止の流れがあります。理由の1つは、主体的な学習を目指すため。与えられた課題をこなすのではなく、自らが必要と感じる内容や興味のある分野について考えながら学習することに期待しているようです。自主的に学びを得る機会を増やすことに賛成する意見もある一方、家庭任せになり格差が生まれ学力低下を心配する声もあります。このような「夏休みをなくす、宿題廃止」の流れについて、学校でも家庭でも話題にしてみてください。
さて、パリオリンピックは観戦されましたか?自宅で多くの種目を観戦しましたが、感動と同時に誤審・誹謗中傷・性別・紛争について色々考えさせられました。8月28日から、パラリンピックが開催されました。
学校には、個性・特性・家庭環境が異なる多様な子が集まります。だからこそ、支援学級や通級・交流及び共同学習の正しい理解が大切です。その子に合った配慮・環境によって落ち着いて学べる場所や時間があることが、子どもの安心の要素となります。パラスポーツを入口に、人権、多様性の尊重、他者や社会との関わりについて知る機会を作るなど、子どものころから先入観をもたないような教育に努めていきたいです。
一年間で1番長い2学期は、運動会、校外学習・修学旅行、音楽祭や市学力調査などの行事が計画されています。子どもたちが夢と希望をもち、充実した日々を積み重ね「実りある2学期」になるよう教職員一同努めていきたいと思います。本校の教育活動に対するご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
7月17日(水)
明日から45日間の長い夏休みになります。子どもたち一人一人が確かな成長を遂げ1学期の終業式を迎えることができ大変うれしく思っています。
先日、3年生に向けて戦争と平和について読み聞かせの機会をいただきました。読み聞かせをする前に日本も戦争をしていたことを少し話しましたが、子どもたちには難しいかもしれないなと思っていました。しかし、聴いている表情から子どもたちそれぞれが戦争、命の大切さについて感じとっていることがわかりました。伝え教えることも大切ですが、日常生活の中で考えたり触れたりするきっかけがあります。そのきっかけを通し「人が嫌がることはしない」「自分や誰かが困っているときは助け合う」ことについて子どもと一緒に話し合って、考えていく。この積み重ねが自分で考え、人を大切にする心を育て、それぞれが成長しながら戦争や平和について見つめ直していく。そんな日々の積み重ねが大切なのだと思いました。
さて、この平和の象徴であるオリンピック、パラリンピックが夏休み期間中、開催されます。1年生から「校長先生は夏休み何が楽しみ?」と聞かれたので「1つはオリンピックかな」と答えると「頑張ってね」と応援してくれました。東京オリンピックの時に2歳~3歳の1年生が知らないのも頷けます。今年のパリ大会には東京大会に続き、成田市出身の橋本大輝選手が男子体操日本代表として出場するのを応援しても楽しいかもしれません。学校を離れての長い時間、「まね」をすることから初めてみてはいかがでしょうか。「まね」をすることかが「学び」につながっていきます。先週、3年生の女の子が「一人で卵を割れるようになった」と教えてくれました。そこからどんな学びに広がっていくのか下記のように考えてみます。
卵料理はどんなものがある? → 材料は? → 安く手に入れるためには? → おいしいレシピはどれ? →
2人分のレシピを4人分にすると調味料の量は? → 料理の記録はタブレット?ノート? → 海外の卵料理は?
ほかにも、図鑑から世界の名画、おじいちゃんのけん玉、動画からリコーダー、新聞の天気図、お姉ちゃんのカレーライスなど興味をもったこと、やってみたいと思ったことと橋渡しをしていただきたいと思います。また、ご家族でのふれあいをより深くし、普段ではできない経験をたくさんさせてあげてください。一緒に本を読んだり野外で活動したり、子どもたちが責任をもってとりくめる手伝いを任せたり、子どもたちの心に残る夏になると良いです。様々な体験を通して大きく成長する夏休み。9月に心も体も大きくなった子どもたちに会えることを楽しみにしています。 また、1学期間、大きな事故もなく生活できましたこと、保護者や地域の皆様のご協力に感謝申し上げます。夏休みも体調に気を付けてお過ごしください。
令和6年6月20日(木)
間もなく入梅となることを思わせる空模様が増えてきました。2年生の育てている一人一鉢の野菜にも花が咲き始め、わかば・ふたば学級の育てている野菜は、一雨ごとにぐんぐん成長し、大きな実を付け始めました。1年生も「きれいな花が咲きますように」と外に出るたびに水やりをしている様子がほほえましいです。
さて、夏休みまでの登校日数が20日となりました。この間、授業参観・引き渡し訓練、3年生の交通安全教室や校外学習などたくさんの行事がありました。5・6年生の代表児童が参加した二部会陸上大会では、壮行会を開き全校で声援を送りました。当日は、猛暑の中、練習の成果を発揮しようと全力で競技に臨む姿やそんな友達を一生懸命応援する新山小の子どもたちを誇らしく思いました。この様子は、先日の全校朝会で子どもたちへ伝えました。また、5月末から水泳学習が始まりました。本年度から民間施設(水泳館)で実施されておりますが、子どもたちからは、「雨でもできる」「コーチの教え方がうまい」と、天候に左右されず学習時間の確保ができ、プロの指導を受けることで水泳に興味をもつなど好評のようです。
PTA美化作業では、休日中にも関わらず作業に参加いただき、心より感謝いたします。おかげであちこち草が生い茂っていた校内外がきれいになり、子どもたちも気持ちよく元気に過ごすことができております。元気がよいのは嬉しいのですが、ケガによる保健室の来室も少なくありません。休み時間の廊下や教室での過ごし方、校庭や遊具の遊び方など、不注意やふざけたことから起こるケガを予防する意識を高め、危険回避能力も育てていけるよう努めていきたいと考えます。ご家庭でも話題に出していただくとありがたいです。
5月の学校便りで紹介した新山小学校のキャラクターについて続報です。たくさんの応募の中から6つの作品が選ばれ、全校児童による選挙で決定します。どのキャラクターも新山小の特徴を捉えており、子どもの素晴らしい創造性に感動しました。今月決定予定ですので7月号で紹介します。
令和6年5月14日(火)
風薫る季節となりました。正門脇の池には、黄菖蒲が咲き誇っています。黄菖蒲(キショウブ)には、その鮮やかで美しい黄色の見た目と、丈夫で強い繁殖力ゆえから「幸せを掴む」という花言葉があります。新山小の子どもたちの幸せを見守ってくれているのかのようです。
4月の授業参観、保護者会、またPTA定期総会へのご出席及びご協力ありがとうございました。おかげさまで各学級、学年の役員さんも決まり、今年度のPTA活動も順調にスタートできました。
さて、新学期がスタートして1ヶ月半。お子様の様子はいかがでしょうか。先日、大型量販店へ行った時のことです。小学校高学年くらいの女の子と母親が買い物をしているときの会話が耳に入ってきました。「何か誤解されているみたいなんだよね。急に話してくれなくなってさあ(子)」「ちゃんと話してみたの?大丈夫よ。わかってくれるって(母)」。新しいクラスになり友達に自分の思いが伝わらず悩んでいることを母親に話していたようです。きっとこういう場面が新山小のご家庭でもあるかもしれないなあと感じるとともに、子どもたちが毎日元気に登校できるのは、温かい家庭生活のおかげと感謝申し上げます。規則正しい生活を営むことや、心がほっと安心できる空間が家庭にあることは、学校生活の基盤となります。これから先、季節も梅雨時期になり疲れもでてくるかもしれません。ご家庭での生活習慣を見直したり、お子さまと日々の出来事を話し合う時間をとったりして頂けるとありがたいです。
さて、本校では、全校児童生徒を6班に分けて縦割り(すくすく班)遊びを進めています。児童会活動や昼の遊びなど高学年がよき手本となり、学習や生活において繋がり安心して学校生活を送れるようにしています。5月2日(木)に、各班ごとに1年生を迎える会が行われました。自己紹介、班別に計画されたレク、写真撮影です。1年生が6年生にぴったりくっつく姿、ぴったりくっつかれて照れくさそうにしている6年生、見ているだけで笑顔になりました。
今年は、6年生の児童会を中心に新山小学校のキャラクターを考えています。現在、アイデアを募集中です。新山小学校らしいみんなにあたたかい校風を感じられるキャラクターになると期待しています。決定しましたら、また学校便りなどを通してお知らせいたします。
令和6年4月17日(水)
暖かな春風に誘われて、校庭では、色とりどりの草花がより一層、その色を鮮やかにしています。保護者の皆様には、お子様のご入学並びにご進級、まことにおめでとうございます。学校では教職員一同、子どもたちが登校してくるのを心待ちにしていました。入学式を無事に挙行し、かわいい28名の1年生、11名の転入生(新入生2名含む)を迎え、全校児童209名、全10学級でスタートしました。
本年度、着任するにあたり新山小学校の沿革誌を手にとりました。昭和52年開校当時の初代校長吉澤茂先生は、「目指す学校像」として「子どもたちが一日一日の中で創造の喜びと精一杯努力した充実感を味わうことができ、次の日の登校が楽しくて待ち遠しいものになるような学校を日々の教育実践の中でつくりあげたい」と記していました。また、そのための具体目標として、教室を「どの子も生き生きと明るくだれとでも自由に話せる」「一人一人の考えが認められ積み重ねられ助け合うことでみんなが伸びていく」場とすることや「健康があらゆる生活の基礎であること」と実践していきたいとも述べています。本校は今年で創立48周年を迎えますが、創立当時から、『みんななかよし 丈夫に育て』という校訓は受け継がれてきたのだと感じました。
入学式でもご挨拶させていただきましたが、子どもたちは、花の種のような存在であり、それぞれの個性、よさがあります。目の前の子供の心の声を聴きながら、そのよさや可能性を引き出し一人一人輝く花を咲かせていけるよう教職員一同、心を込めて育てて参ります。教育は、学校だけでは成り立ちません。保護者、地域の皆様と手を取り合い協働していくことが不可欠です。本年度も本校の教育活動に温かいご支援、ご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。